今では、ほとんどの人がサブスク動画でアニメを見ています。20代なら当たり前ですし、30代でも男女問わずアニメ好きが多いことでしょう。
そんな環境ですが、「マンガが嫌い」「どうしても馴染めない」という人も意外と多いものです。好きな人や友人や同僚がマンガの話題で盛り上がる中、「自分だけ楽しめない」と感じる場面もあるかもしれません。
その理由を考えたことはありますか?
この記事では、マンガ嫌いな人が感じる3つのギャップについて詳しく掘り下げていきます。それぞれの理由を解説しながら、マンガを苦手と感じる方が少しでも新しい視点を得られる内容をお届けします。
アニメの話ができない?なぜマンガが苦手?嫌いな人が感じるその理由
マンガ嫌いの背景には、絵柄やストーリー展開、さらには文化的なハードルといった複数の要因が絡んでいます。これらはどれも個人の価値観や感受性に深く関わるため、嫌いと感じること自体に問題はありません。
ただ、会話を通してコミュニケーションをとりたい方は、例えば国民的人気アニメ「鬼滅の刃」とか「ワンピース」とか少しは知っておいた方がいいアニメもあることでしょう。
まずは「なぜ苦手なのか?」その背景を知ることで「新しい楽しみ方」や「他の人との共通話題」を見つけるヒントになるかもしれません。
嫌いな人が感じる3つのギャップ
マンガを嫌いと感じる理由は、単に「興味がない」だけでは説明できない場合が多いです。むしろ、そこには心理的なギャップが関係しています。このギャップが読者の心に壁を作り、マンガを楽しめない原因となるのです。
本記事では、特に以下の3つのギャップについて解説します。
-
ストーリー展開が「浅い」と感じるギャップ
マンガ独特のテンポ感や物語の構成が、深みを求める読者にとって満足感を欠く場合があります。 -
絵柄への違和感と感情移入の難しさ
マンガ特有のビジュアル表現や記号的な描写が、馴染めないと感じる理由を掘り下げます。 -
マンガ文化に馴染めない心理的なハードル
マンガというメディアそのものに対する偏見や文化的なギャップについて解説します。
これらのポイントを知ることで、マンガに対する理解が深まり、視点を少し変えるきっかけになるかもしれません。
次に、それぞれのギャップに対する解決策やヒントを紹介します。
1. ストーリー展開が「浅い」と感じる理由
マンガが苦手な人の中には、「ストーリーが浅く感じられる」という意見を持つ人がいます。その背景には、マンガというメディア特有の物語構成や表現方法が関係しています。
マンガは一般的に、文字や文章よりも絵を主体として物語を伝えるメディアです。そのため、キャラクターの感情や場面の展開を絵と少量の台詞で表現することが多く、小説のように詳細な心理描写や背景説明が省略されがちです。この省略が、「物語が急展開すぎる」「キャラクターの行動が唐突に感じる」といった印象を与えることがあります。
また、マンガの連載形式も影響しています。週刊誌や月刊誌での連載を考慮し、1話ごとに一定の盛り上がりを作る必要があるため、ストーリー全体の流れが軽く見える場合があるのです。特に短編のマンガでは、読者の興味をすぐに引きつける必要があるため、深みのあるストーリーを構築する時間が限られます。
一方で、すべてのマンガが浅いわけではありません。例えば、『20世紀少年』や『ブラックジャックによろしく』のような長編やテーマ性の強い作品では、心理描写や物語の奥深さを感じることができるでしょう。こうした作品を通じて、「マンガ=浅い」という固定観念を少しずつ崩していくことができるかもしれません。
2. 絵柄への違和感と感情移入の難しさ
マンガが苦手な理由として「絵柄への違和感」を挙げる人は多いです。この絵柄の問題は、マンガを構成するビジュアル表現そのものが心理的な壁となる場合があります。
まず、マンガ特有のキャラクターデザインが挙げられます。例えば、現実とかけ離れた体型や大きすぎる目、極端に誇張された表情などは、「リアリティがない」と感じさせる要因です。これにより、キャラクターに感情移入できず、物語自体に興味が湧かないという結果に繋がることもあります。
さらに、擬音語や記号的な演出(「ドン!」「ギュイン!」など)も、馴染みのない人にとっては過剰に感じられる場合があります。これらは、マンガのストーリーテリングを補完するために使用される重要な要素ですが、「子どもっぽい」「非現実的」と捉えられることも少なくありません。
しかし、マンガの絵柄は非常に多様で、万人向けではない作品も多い中で、自分の感覚に合う絵柄の作品を探すことは可能です。例えば、リアル志向の絵柄やシンプルで洗練されたデザインのマンガは、違和感を軽減する一助となるでしょう。『PLUTO』や『ゴールデンカムイ』などは、写実的な描写を多用しているため、初心者にも入りやすいとされています。
3. マンガ文化に馴染めない心理的なハードル
マンガが苦手な理由として、その文化に対する心理的な抵抗を挙げる人もいます。特に、マンガが持つ独特の表現や、日本を中心としたマンガ文化の特性が馴染めない原因となることがあります。
例えば、マンガ文化には擬音語や擬態語、記号的な描写が多用されます。これらは、感情や行動を視覚的に分かりやすく伝えるためのものですが、慣れていない人にとっては「子ども向け」「非現実的」と感じることも少なくありません。また、コマの読み順やセリフの位置などのレイアウトに慣れていない場合、マンガを読むのが「疲れる」「混乱する」という印象を持つこともあります。
さらに、「マンガは子どもっぽいもの」という先入観が、文化的な壁を作る場合もあります。特に海外では、大人がマンガを楽しむことに抵抗を感じるケースがあり、それがマンガ文化そのものに対する偏見を助長することもあります。
しかし、マンガのジャンルは非常に幅広く、文学、哲学、歴史、SFなど、大人が楽しめる作品が数多く存在します。たとえば、『ヴィンランド・サガ』は北欧の歴史に基づいた壮大なストーリーを展開しており、マンガ文化を理解する第一歩として適しています。また、『MONSTER』のように海外でも評価の高い作品は、マンガに対する先入観を払拭するのに役立つでしょう。
まとめ
今回の記事では、マンガが苦手、嫌いと感じる人が抱える3つのギャップについて解説しました。
以下に要点をまとめます。
-
ストーリー展開が「浅い」と感じる理由
マンガ特有のテンポや描写方法が、一部の読者にとって不満となることがあります。 -
絵柄への違和感と感情移入の難しさ
ビジュアル表現や記号的な描写が読者の好みに合わず、物語に入り込めない原因になることがあります。 -
マンガ文化に馴染めない心理的なハードル
コミック表現やマンガに対する偏見が、心理的な壁を作る要因になっています。
これらのギャップは、マンガ嫌いを助長する要因となりますが、逆にそれらを理解し、自分に合った作品を選ぶことで、マンガの新しい魅力に気づけるかもしれませんし、人生を豊かにするきっかけとなるかもしれません。
まずは、好きな人が好きな漫画やアニメからはじめたり、興味の持てるジャンルやテーマから一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
マンガ嫌いを克服することで、新しい出会いや人との会話の幅を広げることができるかもしれません。もしかしたら食わず嫌いで、「意外とわたしマンガ好きだった」という気づきがあるかもしれませんよ!
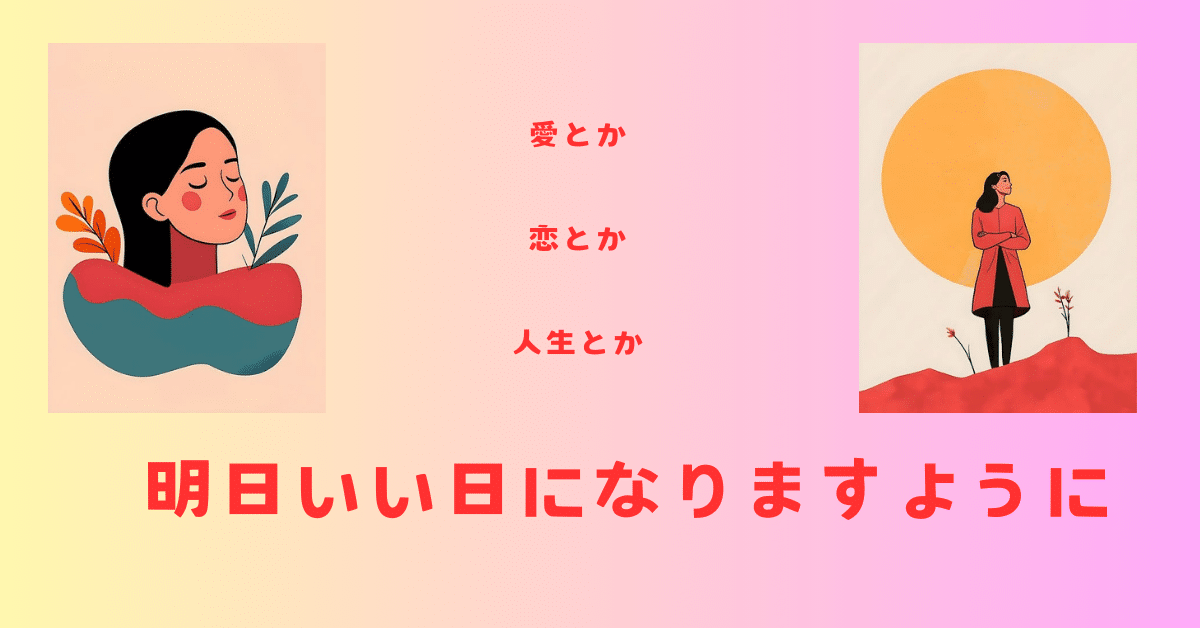



コメント